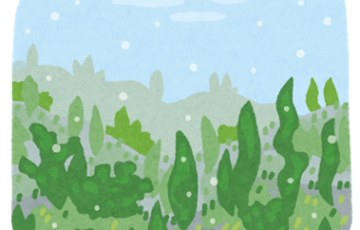「ユニクロ対ZARA」を執筆した齊藤孝浩さんによると、トレンド重視でシーズンごとに大量に商品を入れ替えるファストファッションの商品は、消費期限が最大で8週間しかないそうです。、2013年にバングラデシュで縫製工場が倒壊し、1,100人もの労働者が犠牲になったことをきっかけに製作された映画「ザ・トゥルー・コスト ~ファストファッション 真の代償~」が昨年公開され、ファストファッションが過酷な労働のもとに成り立っていることを伝えました。
こういった多くのファストファッションを運営する企業では、人権保護団体の調査によって縫製労働者の低すぎる賃金設定と、人体に有害な化学薬品の異臭が立ち込める工場での危険な労働環境など、劣悪な環境下で製造されている可能性が高いにも関わらず、何の疑いもなく私たちの生活に溶け込んでいます。

↑日本人が着ている衣服は、度を越す過酷な労働によって成り立っている。
広告やマーケティング戦略によって「安いものはお得」だと一方的に刷り込まれてきた多くの先進国の消費者は、「中国製」や「ファストフード」なども含めて「安いものは質がよくない」という情報には敏感でも、自分たちが安さを追求すればするほど、異国で搾取される人がいて犠牲が増えていくということまでは、なかなか意識することはできていません。世界の格差を無くすはずであったグローバリゼーションはむしろ、お金の力によって圧倒的な勝ち組と負け組みを作り出す構造を生み出してしまいました。
おおもとをたどれば、大量の労働力に頼るようになったのは、16世紀の砂糖のプランテーションに始まりますが、チョコレートやコーヒー、そしてファッションなど、先進国で大量に消費されているものは、今なお「奴隷」という言葉から「契約労働者」や「年季勤務」などと呼び名を変えた発展途上国の労働力に支えられており、国連で現代の奴隷問題について研究しているケビン・ベイルス教授も、「今ではブレスレットや花火などといったものまで、発展途上国の奴隷労働によって成り立っている」と述べています。

↑安さを求めれば求めるほど、異国での搾取が増えていく 。
食べ物から衣服・電化製品まで、さまざまなものが世界を行き交うグローバル社会では、企業は世界市場での価格競争に勝とうと、国境を越えてより安価な労働力を求めるようになり、奴隷のように働かされる労働者も年々増える一方で、その数は2014年には世界で約3,600万人と見積もられました。その数は2012年と比べると、たった2年間でほぼ2倍になっています。
どこに行っても手に入るペットボトル飲料やビニール傘など、安くて手軽な商品は、大量生産のシステムでできていますが、大量生産は大量消費に加えて、「大量廃棄」という習慣も生み出し、消費者が当たり前のようにモノを使い捨て始めたように、大量に存在する発展途上国の労働者もモノのように使い捨てられるようになってしまったのかもしれません。

↑人も大量生産のモノのように、必要に応じて使われ、切り捨てられる。
使い捨てのモノように扱われている労働者の実情は、昨今NGOなどのウェブサイトやドキュメンタリーなどでも知ることができるようになってきており、2000年にイギリスで放映されたドキュメンタリー「Slavery: A Global Investigation」(奴隷制:その全容を探る)で、カカオプランテーションで保護されたおびただしい数の傷跡を持つ少年が、先進国のチョコレートの消費者に向かって発した次の言葉が、大きな議論を呼びました。
「彼ら(チョコレートを食べている人)は、オレの肉を食べている。」
その言葉は、強烈なインパクトをもって世界中に拡散され、チョコレート企業には消費者からの抗議の電話や、不買運動を匂わす手紙が送られてくるなどの反響がありました。
おそらく私たちを含む先進国の消費者が、すぐに不買運動につなげてしまうのは、「みんなが買わなければ、その品物は出回らなくなるので、きちんとした品物だけが残るようになる」と、考えるためかもしれませんが、残念ながら買わないことと、労働者が正当に扱ってもらえるようになるということは、必ずしもイコールではなく、買わないという運動は、労働者を経済から完全に切り離してしまう危険性があることもしっかりと意識しておかなければなりません。

↑チョコレートを食べている人は、オレの肉を食べている 。
このドキュメンタリー以前に、アメリカで衣料品における児童強制労働が明らかになった際には、議員によって提示された「児童労働によって生産された製品の輸入を禁止する」という法案に対し、先手を打とうとしたある企業によって、突如として解雇されたバングラデシュの5万人の子供たちが行き場を失い、人身売買業者の手に渡ったり、もっと危険な仕事につかざるをえず、皮肉にも不買運動の結果、一番苦しむことになったのは助けようとした子供たちでした。
こういった動きをはじめとした政府の対策に対し、NGO「セーブ・ザ・チルドレン」のアニータ・シエスさんは、経験不足と無知によってNGOの活動が台無しにされたと考え、子供を守るという本来の目的を忘れてはいけないとして、次のように述べています。
「目的は労働から害をなくすことで、労働の場から子供を無理に連れ出そうすることではありません。子供が仕事を得ることも必要な場合があるし、子供たち自身が仕事を得たがっている場合もあるのです。」

↑強制労働から救うつもりが、もっと過酷な状況を作り出してしまう。
カカオ豆の強制労働について、「児童強制労働をしていません」と証明するラベルを貼るという案が出た際に、チョコレート企業はこの発案者であった議員のところに押しかけ、農場に確認をすると言うのでなく、「会社をつぶす気か」と訴えたといいますが、前述のケビン・ベイルス教授も、消費者がすべきことは、すべての人に正当な賃金を支払っているという証がついているものだけを選ぶことだと述べています。
オーガニック・チョコレートブランドを展開するグリーン・アンド・ブラックス社を設立したクレイグ・サムズさんも、「良心的な消費」の機運が高まるかどうかは、生産者より消費者の問題だと指摘しており、消費者が「公正の保証」をされた商品を買って、「自分も問題解決に役に立つことができた」と感じられることが大事であり、それは現代の消費者が環境問題や温暖化など、確実に自分の生活が地球に悪影響を与えていると認識し始めている中で、商品の味よりも何倍も重要な意味を持つようになってくるでしょう。

↑搾取しないモデルを作るために、正しいものを「高く」売る。
グリーン・アンド・ブラックス社は、「公正の保証」として「フェアトレード」の認証を用いていますが、フェアトレードは消費者を倫理的に満足させるだけではなく、農民はフェアトレードによって取引価格が保証されたことで、より質の良いカカオ豆を生産するようになり、収入の増えた農民のほとんどは子供を学校に通わせることができるようになったため、その地域で10%だった高校への登録率が70%に増えるという好循環が生まれました。
フェアトレードによって、農民の収入に少しでもゆとりができ、農民が進んで新たな取り組みに投資をする事例も増えていて、西アフリカのフェアトレード・カカオ団体では、フェアトレード本部のアドバイスよりも10%も多い額を投資にまわし、カカオ豆の品質を上げようと努めており、フェアトレード・アフリカ支部のアダム・タンプリさんは次のように語っています。
「農民が集まり、収入を得て投資ができれば、自分たちで問題を解決することができるようになります。」

↑搾取を無くし、さらに質の良いものができる好循環を作り出す。
ナイキも、1990年代に過酷な労働がメディアに晒され、それを認めて監査を増やすことを誓い、その報告を重ねることで消費者を納得させましたが、現代の情報化社会では、強制労働が企業の下請け会社で行われていることであっても「知らなかった」では通じず、たとえ価格を上げることになったとしても、末端の人々と一緒に健全な経済のあり方に向けて取り組むほうが、問題の解決へと発展していくのではないでしょうか。
2005年に、チョコレート企業の大手キャドバリーが、グリーン・アンド・ブラックス社を買収し、今ではキャドバリーが自社のチョコレートバーにもフェアトレード認証を受けたように、大企業が「良心的」なブランドを買収したり、立ち上げたりしていることも多く見られるようになりました。
消費者がおおもとの労働者にまで「公正」ということを求め続けていれば、大企業の悪しき文化を、買収された側の良心的な企業が塗り替えることも十分可能であり、こういった事例が増えていけば、一気に「フェアな経済」が現実的なものになっていくのかもしれません。
※参考文献
キャロル・オフ 「チョコレートの真実」 (英治出版、2007年)