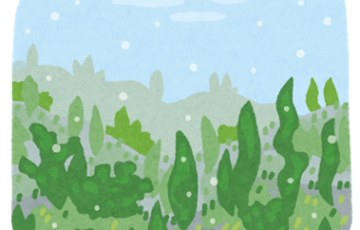アメリカ政府が、大さじ2杯分のトマトペーストが使われたピザであればトマトと同等の野菜であるとみなし、じゃがいもから作られるフライドポテトは新鮮な野菜と同等であると主張しているように、多くのメニューがファーストフードとなっているアメリカの学校給食は新鮮な野菜が不足していることもあって、3分の1以上の子供が肥満に陥っています。
アメリカでは、ケチャップやフライドポテトはよく知られているのにも関わらず、その原材料であるトマトやじゃがいもがどんな野菜なのかを知らない子供たちがいるそうで、食についての知識不足が子供たちの健康に悪影響を及ぼしているのかもしれません。

↑アメリカではトマトやじゃがいもがどんな野菜なのかを知らない子供たちが現実に存在する。
日本でも子供の食生活は決して良い状況にあるとは言えず、健康的な食事は学校給食で提供されているからと、コンビニで買ってきたお惣菜や加工品などの健康的ではない食品ばかりが食卓にあがる家庭も珍しくなく、アメリカの子供たち同様に日本の子供たちも、健康被害の危機にさらされていると言っても過言ではないようです。
忙しい毎日を送るわたしたちのライフスタイルがより便利な生活を求め続けさせ、食事までもが利便性の対象となってしまったことで数多くのファーストフード店が蔓延しました。
こういったファーストフードやコンビニ、そしてスーパーに並んでいる数多くのスナック菓子などを見ても、そのほとんどの材料は小麦、じゃがいも、そしてトウモロコシなど似たようなものばかりであり、食べるものの選択肢は豊かになった反面、栄養価の面では質素なものへと変化しています。

↑食べ物の選択が増えれば増えるほど、栄養素はどんどん貧しくなっていく。
保存ができて手間暇をかけずに食事を済ませられる加工食品は、塩分、糖分、そして脂質を多く含んでいますが、添加物によって味が操作されているため、本来であればおいしいものは安全だと感じるはずの私たちの味覚に頼ることはできなくなっていて、もともと添加物を売る側にいた安部司氏は著書「食品の裏側2」で次のように述べています。
「食塩10gの入った水は飲めないけれど、同じ塩分量でもカップ麵ならおいしく食べてしまう。砂糖50gの入った水も飲めないけれど、同じ糖分量の清涼飲料水なら平気で飲める。」(1)

↑砂糖50gの入った水は飲めないけれど、同じ糖分量の清涼飲料水なら平気で飲める。
自然から離れた食品を食べるようになったことは、わたしたちの大切な食生活はおろか、健康に影響を及ぼし、かつては成人病とされていた肥満、高血圧、そして糖尿病が子供たちの間で広まりつつあり、生活習慣病の予備軍は10人に4人とまで言われるようになってしまいました。
そんな中、子供たちの食の原点に対する興味や関心を引き出そうと、農家に協力をしてもらって食育に取り組む学校が出てきています。
自然が多い田舎で暮らす子供たちであれば、草花を使った遊びや虫とりのほか、山菜を採りにいったり果物狩りをしたり、普段の生活に自然が結びついていますが、都会で暮らす子供たちにとって、町の中で目にする木や花は、所詮人の手によって植えられたもので、普段の生活で本当の自然に触れる機会はめったにないため、まだ根も葉も付いたままの調理する前の野菜に触れることは、現代の子供たちにとって効果的な食の「教材」になるのだそうです。

↑自然界に存在しない添加物を大量に消費するのは、自然に触れることを忘れてしまっているから。
実際に、畑や田んぼが縁遠い都会の町で大根作りにチャレンジした江東区の小学生は、自分たちで野菜を育て収穫するという経験を通して、虫や小動物が好きになったなど自然に関心を持つようになり、また、保護者からは「子供が食べ物を残さなくなった」という報告もあったそうです。
千葉県市川市にある行徳小学校では、伝統行事などの地域文化や食材の歴史など、社会学習に「食」を積極的に取り入れており、この小学校にどの食材がどこでどのように作られているかが分かる手作りの地図を提供し、食育をサポートしている管理栄養士の高橋恵美子さんも、採れたての野菜と触れる体験について次のように述べています。
「食べるという行為はほかの命をいただくことだということを、やはり知ってほしい。最初の頃、キャベツを根っこから持ってきてもらって、子どもたちに見せたことがあるのですが、弾けるくらいに新鮮でピカピカのキャベツを初めて見て、これが本物かと驚く子どもが大勢いました。実際に採れたての新鮮なキャベツを食べると、子どもたちはその甘さやおいしさをきちんと理解できる。体全体で、おいしさを感じ取れるんですね。」(3)

↑食べるという行為はほかの命をいただく行為。
このような学校と農園を繋げ食育の場を広げていこうという動きはアメリカ各地でも見られ、校庭の一部を農園に変える「食べられる校庭(エディブル・スクールヤード)」と呼ばれる運動がありますが、この取り組みはアリス・ウォータースという一人の女性から始まったものでした。
彼女は毎日の通勤時、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア中学校の前を通っており、この中学校の校庭が荒れ果てていたことに疑問を感じ、新聞に問題提起の投稿をします。その記事を読んだ同校の校長がウォータース氏に連絡を取ったことで「食べられる校庭」の設置に発展していったのです。

↑荒れ果てた校庭を「食べられる校庭」へ。
実はアリス・ウォータース氏は、地元で採れた旬のオーガニック食材を使った料理を提供する、アメリカで人気のレストラン「シェ・パニーズ」の創設者だったのですが、栄養バランスの取れた食事は、子供のうちから学ぶべきだと考えており、実際に野菜や果物に触れることが効果的な教育方法だとして、学校に農園とキッチンを設置することを計画しました。そうして、今から約20年前にカリフォルニア州バークレーにあるマーティン・ルーサー・キング・ジュニア中学校で初めての「食べられる校庭」が誕生したのです。
それから現在まで、「食べられる校庭」はアメリカ国内で徐々に広まりつつあり、子供たちの食に対する関心に変化を与えています。以前は「サラダなんて敵だ!」と言っていた子供が、野菜がたっぷり詰められたパンを美味しそうに食べるようになったりなど、それは保護者も驚かせるくらいで、実際に農園で野菜や果物の成長に触れることが、食に関心を持たせる効果的な方法になっているようです。

↑実際に自分の手で栽培してみると、ここまで大きな変化が出る。
農園が持つ力は食育の他にもあり、ドイツのライプチヒ市にある、農場が併設されたモルカウ幼稚園に通う園児の中には、知覚障害や自閉症などの障害を持った子供もいるのですが、障害の有無に関わらず、園児一人ひとりが自分ができる範囲の農園の仕事に携わることで、個々の長所を伸ばしていっているのだそうです。
まだ力のない子供ですから、当然ながら作業は仲間と力を合わせながら進めなければならず、これが助け合いや支え合いを学ぶ良いきっかけになるのだと言い、園長のドレヴァーマンさんは次のように述べています。
「種をまき、水をやると、子どもが成長するように植物も育ちます。収穫した後、自分たちの手で育てた野菜を洗う子どもたちの満足げな顔は、なにものにも代え難いものです。」(4)

↑自分たちで育てた野菜を収穫した後の子どもたちの満足げな顔はなにものにも代え難い。
人口の約8割が農民だったと言われている終戦直後の日本では、子供も重要な労働力であり、農園と人が密接に結びついていたからこそ、「いただきます」と手を合わせて、米粒一つ残さず食べることが当然であったのかもしれません。
それが、農園がわたしたちから遠い存在となってしまった現在では、好きなものだけを食べ、嫌いなものは食べないという子供が増え、最近では「子供には嫌いなものは無理して食べさせなくてもいい」という保護者までもがいると言います。(5)
食べることに対する感謝の気持ちが薄れ、手っ取り早くお腹だけを満たしてくれる栄養価の低い食品が溢れている時代だからこそ、子供たちには食べることの大切さだけではなく、何を食べるかを選択することの重要性も教えていかなければならず、それは教科書よりも、実際に農園で野菜や果物作りに携わることがもっとも効果的な教材となるようです。
《参考文献》
1.安部 司 「食品の裏側2 実態編: やっぱり大好き食品添加物」 (2014年、東洋経済新報社)
2.金丸 弘美 「給食で育つ賢い子ども」 (2008年、木楽舎)
3.金丸 弘美 「給食で育つ賢い子ども」 (2008年、木楽舎)
4.近藤 まなみ、兼坂 さくら 「グリーン・ケアの秘める力」 (2008年、創森社)
5.福岡 正信 「自然農法 わら一本の革命」 (2009年、春秋社)