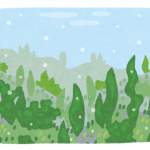- 機能性発酵飲料「_SHIP KOMBUCHA」の製造販売
- 100% Plant-Based/Naturalな素材にこだわったカフェ「1110 CAFE/BAKERY(川口市領家)、「BROOKS GREENLIT CAFE(港区南青山)」の運営
- 約3000坪の自社敷地を活用した各種イベントを開催
- 自社農場で野菜の有機栽培に挑戦
- サーキュラーエコノミーの実践 などなど
素敵な環境を創造し続け、世の中を笑顔で満たす活動をしている、大泉工場のKANです。
「渇望の循環」というテーマを考えていたとき、ふと頭に浮かんだのが、一見突飛な存在ともいえる漫画『ワンパンマン』だった。
この作品には、自らの限られた資源をもとに動き、周囲を巻き込みながら世界を変えていく──そんな“エフェクチュエーション※的”な精神が、確かに宿っている。
そしてそれは、今、僕たちが取り組んでいるプロジェクトにも、通じていると感じている。だからこそ今回は、この漫画を一つの「渇望の循環」として読み解いてみたい。
※エフェクチュエーションとは…
「今あるもので何ができるか」を考えて行動を始める、考え方。
大きな目標や完璧な計画がなくても、手元にある人脈・知識・スキルを活かして、小さな一歩から動き出す。
やがて仲間が現れ、目的が変わりながら、流れの中で未来を形づくっていくアプローチ。
5つの原則(手中の鳥/許容可能な損失/クレイジーキルト/レモネード/飛行中のパイロット)に基づいて展開される。
『ワンパンマン』という漫画をご存知だろうか?
となりのヤングジャンプという、集英社が運営するWebコミック配信サイトで連載されている、ある意味“最強の構造”を持った作品だ。
アニメとしても世界的な人気を博しているこの『ワンパンマン』だが、その出発点には、驚くべき原作が存在する。
今から10年以上前、偶然見かけた「このWeb漫画がすごい」という記事。
そこから飛んだ先にあったのが、今なお無料で閲覧できる、ONE氏による原作『ワンパンマン』だった。
最初に衝撃を受けたのは、画力の“異質さ”だった。
プロ漫画家の水準と比べれば、正直、稚拙に映る──だがそれ以上に、その“描かずにはいられなかった衝動”が、画面全体から滲み出ていた。
この作品は、作者であるONE氏が、自身のWebスキルを磨くために始めたという。
つまりこれは、評価のためでも、収益のためでもなく、内なる動機から生まれた創作だった。
次に驚いたのが、ストーリーの構造である。
主人公は、あらゆる敵を“ワンパン”で倒す最強の存在。
だが、決して最初から現れるわけではない。街に危機が訪れ、ヒーローたちが苦戦し、絶望が訪れたその時に、遅れて彼はやってくる。
そして一発で、すべてを終わらせる。
この“遅れてやってくる最強”という構造にこそ、この作品の中毒性がある。
登場人物たちは、各々の「戦う理由」を持っている。信念や過去、名誉や愛。それらが色濃く描かれた上で、主人公の「ワンパン」が問題をすべて片付けてしまう。
そのギャップが、読者の深層にある“解決願望”を鋭く刺激してくる。
そして何より特筆すべきは、この作品が後に、プロ漫画界隈でも圧倒的画力を持つと言われているプロ漫画家・村田雄介氏(代表作:アイシールド21)によってリメイクされ、世界に羽ばたいていくことになった点だ。
原作を描いたONE氏に対し、村田氏の方から「リメイクさせてほしい」とオファーがあったという。
素人が無料で公開していたWeb漫画を、プロが見つけ、惚れ込み、手を差し伸べ、再構築する──。
これは、かつての常識ではありえなかった物語だ。
だけど僕は、この展開を“シンデレラストーリー”とは呼ばない。
これは、構造の話だ。
Webという開かれたプラットフォームに、自分の未完成な作品を、恐れずに投げ込む。
フィードバックも評価も整わぬままに、それでも発信をやめない。
その継続の中で、偶然が意味を持ちはじめ、出会いが訪れ、循環が生まれていく。
これは単なる運ではなく、「許容可能な損失」の中で、熱狂を燃やし続けた結果だ。
そしてその熱狂こそが、人を惹きつけ、世界を巻き込み、想像を超えた変化を呼び込むのだと思う。
実際、僕自身も過去に、未完成のまま世に出した企画がある。
当時は恥ずかしさもあったが、それでも「今の自分にできることを形にして届けたい」という気持ちのほうが強かった。
不思議なことに、その企画が誰かの目にとまり、予想外のコラボや応援の声が生まれた。
僕一人では到底届かない場所に、その“未完成”が連れていってくれた感覚がある。
やはり、何も始めないことこそが、最大の損失なのだと思う。
気づけば、僕もまた、原作の更新日を心待ちにする“渇望者”の一人になっていた。
与えられるのを待つのではなく、自分の内にある熱を手がかりに、未完成のままでも投げてみる。
その先でまた、新しい“出会いの連鎖”が始まるかもしれない。
だからこそ、僕たちのプロジェクトにも、この“渇望の循環”が生まれてほしいと願っている。
渇望とは、欠けているからこそ生まれる感情だ。
満たされない状態が、行動を生み、誰かの共鳴を呼ぶ。
その共鳴が次なる渇望を生み、また誰かの衝動を刺激する──そうして循環は生まれていく。
だからこそ、完成されたものよりも、むしろ“余白”のあるものの方が、次の何かを誘発する力を持っているのかもしれない。
つまり、「渇望」は、終わりではなく“始まり”のサインなのだ。
僕たちが運営する株式会社大泉工場でも、人々の内にある渇望を起点に、新たなプロジェクトが次々と生まれています。
もし少しでも「一緒に循環をつくってみたい」と感じた方がいれば、ぜひ下記のリクルートサイトをのぞいてみてください。